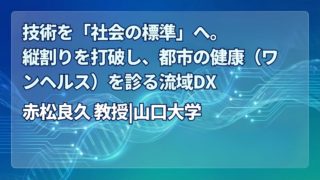【前編】「生物に万能な支配方程式はない」水工学の限界に挑む流域DX
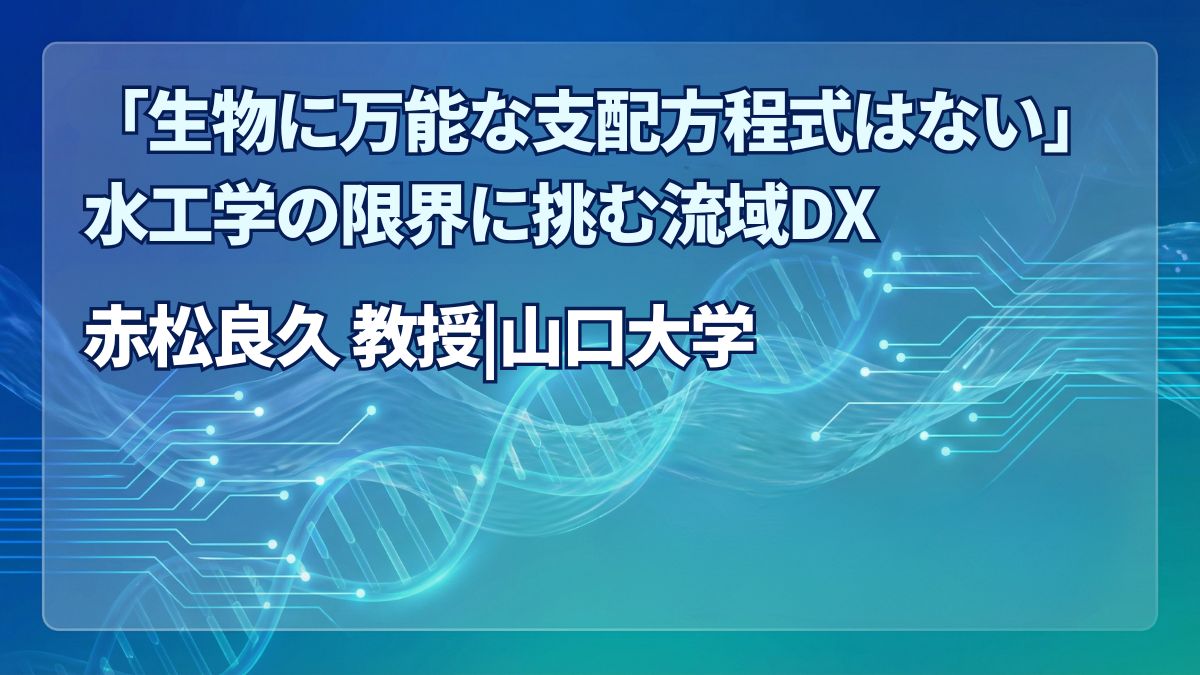
日本のインフラ管理は現在、「災害対策」と「環境保全」という二律背反する課題に直面しています。洪水や高潮などの水害から人命や財産を守るため、川を制御し、水を管理する「治水」の分野では物理シミュレーションによる予測手法が確立している一方、生態系への影響に関しては、長らく定量的な評価が困難であり、「経験と勘」に頼らざるを得ないのが実情でした。
この課題に対し、河川の物理現象を専門とする水工学の立場から、「環境DNA」という技術やAIなどのテクノロジーを使って、生物・生態系や地球環境、防災・減災に関わる幅広い研究を行っているのが、山口大学の赤松良久教授です。
従来の土木の枠を超えて、他分野とも連携しながら研究に取り組む赤松氏。前編では、その研究の原点と、技術の可能性について伺います。
話を聞いた人

赤松 良久 氏
山口大学 大学院創成科学研究科 教授
博士(工学)。地域レジリエンス研究センター長。環境。専門の水工学・水工水理学を基盤に、生態学やAI・ドローン技術を融合した「流域DX」を推進。国土交通省等の受託研究、民間企業との共同研究を通じて社会実装を牽引する。
https://ds.cc.yamaguchi-u.ac.jp/~yakamats/index.html
「生物には方程式がない」
水環境保全や水災害対策など、水に関わる学問である水工学を専門とする赤松氏。
「流域という広大なものを相手した時は、既存の技術では厳しい」
この気づきが、現在、AIなどの最先端技術を駆使しながら研究に取り組んでいる原点となっています。そんな技術の限界に直面したのは博士課程の頃。当時取り組んでいた、沖縄の赤土流出やサンゴ礁の保全に関する研究がきっかけでした。
「沖縄では、マングローブ林が赤土を溜め込んで流出を抑えており、それによってその沿岸域にサンゴ礁が育ちます。さらに、その環境でいろいろな生物が生息し、マングローブもそれを基盤として維持されていく。いろいろなものが、そのバランスの中で生きているんです。
流域の水や物質の循環、動態によって他のものも変わっていく。その気付きから、物理的な現象だけでなく、生物なども含むより本質的な部分で何が起きているかを把握する必要があると感じました」
物理現象には「支配方程式」があります。これは、物理現象を記述した方程式のことです。水や土砂の動きにもこの支配方程式があり、それによって動きを推測することができます。しかし、生物に関してはそのような方程式はありません。そのため、生物の分布や変化などを推測するには統計モデルに頼るしかなく、莫大なデータが必要になるのです。その難しさを赤松氏はこう話します。
「データを取るために、生物を獲って数えたり、目で見て特定の魚をカウントしたり…。特殊な能力や知見が必要な上、ものすごい労力がかかります。そういう従来の採取方法では、ビッグデータの取得は難しい。分析で使えるデータを取るには、この方法では無理だと思いました」
その気付きが、生物情報を「客観的な数値データ」として取得し、工学的に扱う現在のアプローチへとつながっています。
「職人技」からの脱却と標準化
この壁を突破するために赤松氏が導入したのが「環境DNA」です。水を汲み、その中のDNAを分析するだけで、水域における生物の生息の有無や密度を明らかにすることができます。赤松氏は、この技術を「圧倒的」と評価します。
「まず、かかる労力が全然違うんです。少ない労力で、広域のビッグデータの取得が簡単にできます。さらに、環境DNAは誰が行ってもほとんど同じ解析結果になります。これは、科学的な解析に使うデータとしてはとても重要なことです。これまでは、採取する人の能力の差によってデータが違ったため、科学的な解析に使うには不十分だと感じていました。環境DNAはこれらの利点から、圧倒的な強みを持った技術なのです」
従来の生物の調査は専門家の“職人技”に依存していた上、広域かつ継続的なモニタリングも難しかった。しかし環境DNAなら、現地の作業は水を汲むだけ。分析のプロセスも標準化することができ、均質なデータを取得することができるのです。
その有効性の高さから、2026年度から国土交通省の「河川水辺の国勢調査」の魚類調査において、環境DNAが導入される予定だといいます。活用が進む環境DNAの可能性について、赤松氏は「これからますます広がっていくと思います」と期待を語ります。
AIによる「環境のデジタルツイン」構築
環境DNAは「予測」への道を切り拓くカギです。赤松氏の研究チームは、環境DNAで得た生物データと、地形や流況などの物理データをAIに学習させ、「生息ポテンシャル」を予測するモデルを構築しています。これにより、「気候変動で流量が変化した際、アユの生息域はどう変わるか」「河川改修が生態系に与えるリスクはどの程度か」といったシナリオ分析が可能になるといいます。
こうした「得られる情報から予測する」ことこそ、まさに赤松氏の実現したいことです。
「環境DNAですべての領域を継続的に調査することは不可能ではありませんが、コストもかかるためにかなり難しい。だから、情報を得て推測するところまでを実現したいのです。将来的には、気候変動によって流量が変わった河川で何が起こるか、なども予測することができるようにしたいと考えています」
こうした予測は、河川管理においても重要な役割を果たします。
従来、水害や土砂災害から命や財産を守るために、川の水量を調整したり、流れる仕組みを整えたりする「治水」の分野では、「先に何が起こるか」をある程度予測しながら整備を進めてきました。しかし、生態系などの環境面については、定量的に影響を評価する方法がなく、計画段階で十分に織り込むことができませんでした。
赤松氏は、この課題について次のように語ります。
「どういうことが予測されるか、定量的な評価法がないと『こういう可能性・リスクがある』という言い方しかできないんですよね。となると、“想定外”をできるだけなくすために、安全策をとることしかできなくなってしまいます。安全の領域からは出られず、進化していかない。その中で、予測によって評価ができるツールを作ることに意義があると感じています」
AIによる予測モデルが整えば、治水と環境を同じ定量的な土俵で議論し、最適解を導く「治水と環境の調和」が可能になります。これまで「想定外」とされてきた環境リスクを、インフラ設計や河川管理の初期段階から織り込んでいく――。それが、赤松氏の描く「流域DX」の姿です。